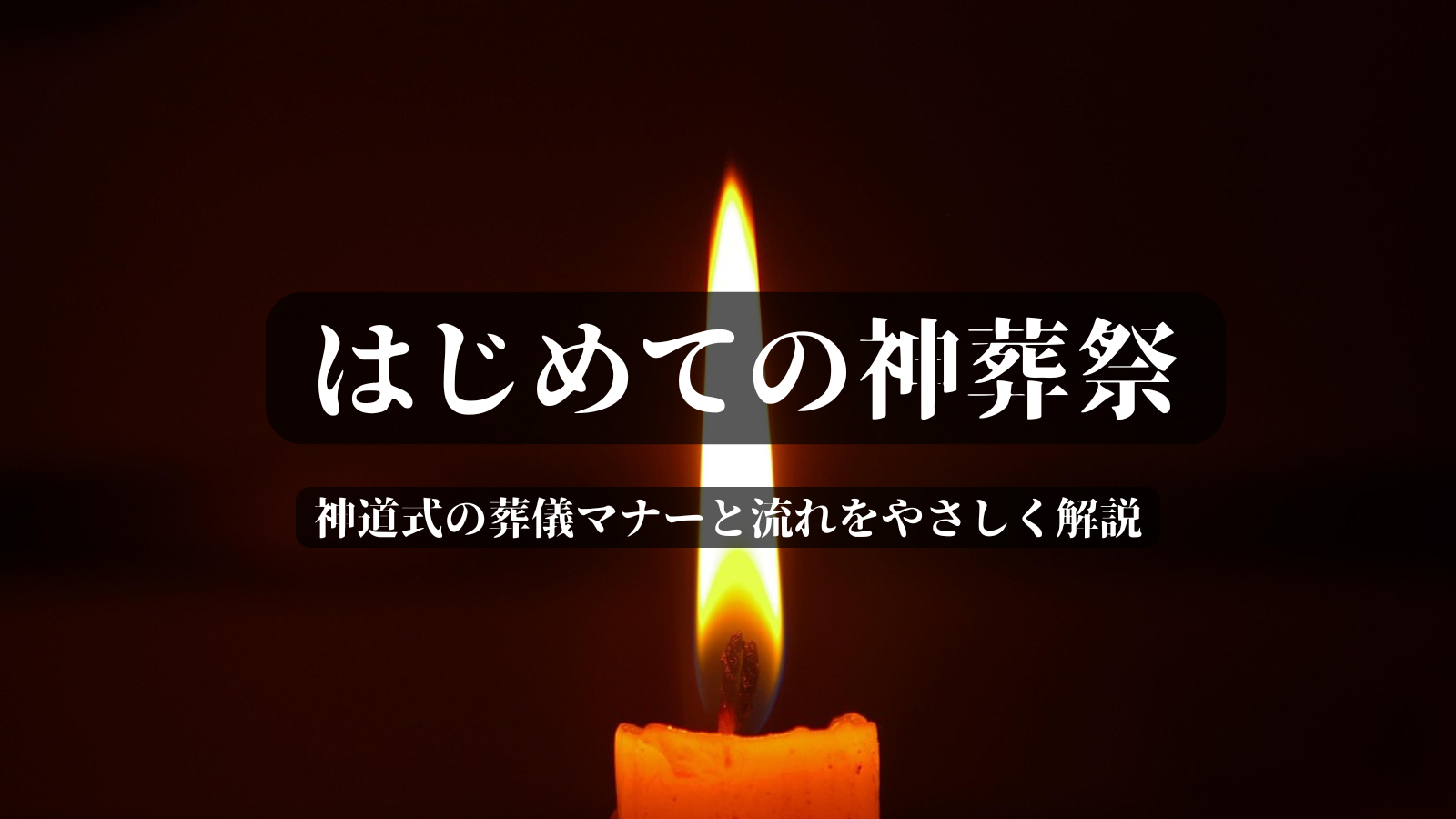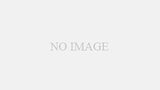今回は、神道の葬儀である神葬祭を、元サラリーマンで現役の神職がご紹介します。
心身ともに大きな影響を与えるストレスは、家族の死だと言われています。
あなたは人間が亡くなると、御霊(魂)はどこに行くと思いますか?天国や地獄に行くのか、やっぱり生まれ変わりをして、全く違う新たな人生を歩むと思いますか。それとも”無”ですかね。
人生で一回経験するかしないかレベルの神道の葬儀である神葬祭で、抑えておきたいポイントをお伝えします。
神道の葬儀 神葬祭とは
神葬祭に参列したことがある人は結構少ないと思います。
葬儀と言えば仏式のお葬式を思い浮かべて、どんなことに気をつければ良いか対応できますが、神葬祭は分からないことだらけだと思います。
神葬祭の特徴は大まかに3つあります。
厳かで慎み深く簡素
各地域特有の特徴がある
制約が少なく費用も抑えられる
安産祈願、初宮詣、七五三など人生の様々な場面で、関わりのあった神社(氏神さま)の神職に神葬祭を執り行うことで、人生儀礼の最後を締めくくります。
神道の考えでは故人の御霊は、どこか遠いところに行ってしまうのではなく、私達が見えないだけで近くに留まり続けていると捉えており、「幽世(かくりよ)」と呼んでいます。
そして故人の御霊は、いつでもそばに留まり続けて守り神として、子孫を見守っているとされており、故人が亡くなったことを「帰幽(きゆ)」と言います。
神道の葬儀 神葬祭の流れ
大切な人を亡くすと大きな悲しみに襲われると同時に非常に忙しくなります。
・逝去した当日
親族や関係者に連絡し葬儀の日程を決め、役所関連手続きもしなければなりません。そして神葬祭を希望するのであれば、神社(神職)に依頼をします。
神葬祭の日程
通夜祭(1日目)葬場祭・火葬・帰家祭(2日目)
※地域によって、祭儀の名前や内容が異なることがあります。筆者が奉職している神社の神葬祭をもとにご紹介いたします。
・帰幽報告 枕直しの儀
神葬祭は氏神様に故人が亡くなった旨を報告することから始まります。
故人を北枕にして顔に白布で覆います。
枕元に枕屏風を立てたり、守り刀を胸元や枕下に置いたりしますが、これらは地域の風習によって異なってきます。
神職は連絡を受けると、すぐに故人のもとに行き祭詞を奏上します。そして喪主と本格的な打ち合わせが始まります。
その時に神葬祭の依頼書や故人がどんな人物だったかの略歴書、神葬祭の大まかな流れが書かれた用紙を渡します。
奏上している祭詞は、毎回それぞれの故人に合わせて作成しています。故人の情報が無いと書けません。ですので、ご遺族に故人はどんな人物だったのか色々と知るために略歴書の提出を必ずお願いしています。
通夜祭・遷霊の儀(1日目)
家族や生前親しかった人が集まり、夜通し故人を偲びます。
本来は故人の蘇りを祈るもので、御霊(魂)を遺体に引き戻そうと、故人とともに盛大に酒宴を設けて復活を願っていました。
コロナ禍以降は縮小しましたが、今でも親族や親しかった者同士で食事を囲む風習が残っていますし、遺族のための夕食の場が設けられているのも、その名残りかもしれません。
この通夜祭は日が沈んだ時間帯に斎行します。
神社や地域によって異なると思いますが、祭儀の前半で遺体から離れた御霊を依り代である霊璽(れいじ)に移し鎮める儀を執り行なった後に、通夜祭の祭詞を奏上します。
・葬場祭・発棺祭(2日目)
故人との最後のお別れをする祭祀です。
祭儀の流れは通夜祭とあまり変わりません。故人の人柄や経歴、功績を称えて、今後はご先祖様と共に遺族と子孫を見守ってくださるように奏上したあと、発棺祭を執り行います。
最後に参列者が故人との訣別を行い退出します。肉親や近親者は安らかな帰幽を祈って対面した後、霊柩を奉じ、葬列をととのえて火葬場へと向かいます。
火葬場では非常にシンプルな祭祀です。祭儀の始めに神職がお祓いし、火葬場祭祭詞を奏上したら神職は退出します。
その日の午後に帰家祭を執り行います。
・帰家祭(2日目)
本来であれば自宅で執り行う祭祀ですが、近年は葬儀会場で行うことが一般的だと思います。
この祭儀も内容はほとんど同じで、祭詞の内容が異なる程度の違いです。
筆者が奉職している神社では、通夜祭と帰家祭の最後に挨拶があります。
挨拶と言ってもお坊さんの説法のように長い時間を要するものではありません。
”神道とはどういう宗教か” ”人間が亡くなった後どうなるのか” ちょっとだけ専門的に分かりやすく2・3分ほど紹介して終わります。
コレが、神葬祭のザックリとした内容です。葬儀社で行なうのであれば司会者がいますし、何かしてもらう場合は神職が説明するので、難しいことは無いと思います。
いつ神主さんにお金を渡すのか、それは帰家祭を行う前に渡します。
軽い挨拶と納骨をいつすべきかの今後の予定が書かれた紙を渡されます。もしくは今まで神道じゃなかったけど、この際に神徒さん(檀家さんと同じ意味)になって、永代供養してもらうご家族もいます。
これは個人の感想ですが、神葬祭は本当に神経を使うので祭祀の中で最も緊張します。葬儀の電話が来たと分かると社務所内はピリつきます。
大往生で老衰で亡くなった場合なら、まだご遺族も現実を受け入れ易いと思いますが、若い年齢で自殺や病死の場合だと、ご遺族はショックで泣いてパニックになっていたり、逆にショック過ぎて冷静で無表情の姿を見ると心がギュッとなります。
神道の葬儀 神葬祭が終わった後
神葬祭後に斎行される祭儀は、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭(納骨)、百日祭、一年祭、二年祭、三年祭とあります。
特に十日祭と五十日祭(仏教の四九日に相当)には、家族や親族が集まり故人を偲びます。
五十日祭を終えると喪が明けます。ご家庭に神棚がある人は、五十日祭を終えると神棚の全面に貼っていた半紙を取り除きます。
そして、多くのご家族は五十日祭を行なう日に納骨をするので、この日だけは祭儀は少し長く時間が掛かってしまいます。
因みに喪が明けるまで神社へのお参りやお祝いごとのイベントへの参加も控えるべきです。喪の期間中に正月を迎える場合は、鮮やかな飾り付けは控えて質素に年を迎えましょう。
もし精神的に優れなくて十日祭なんて出来ない場合は、体調を整えることを優先して欲しいです。神社としては、そんな無理強いはしないので、連絡すれば大丈夫です。
神道の葬儀 穢れと喪
現代においては、穢れや喪は感覚の問題になると思います。
しかし、古代の日本人は相当シビアだったと思います。今は亡くなった人のご遺体は徹底的に管理されますが、昔はそんなことは出来ません。
何らかのウイルス・病原菌が遺族に移っていた場合、その遺族が撒き散らしてしまうと、疫病として甚大な影響を与えてしまうことになります。
だからこそ、昔の日本人はそれを”穢れ”と捉え、人が亡くなると”喪”の期間を設けたと考えられます。
神葬祭 作法&マナー
さて、神葬祭に参列中に何をするのか知っておきたいハズです。
参列者が行うことは、斎主一拝、玉串拝礼だけです。
・斎主一拝
コレは祭儀の初めと終わりに一礼するものです。参列者のタイミングで起立して一礼するのではなく、神職が丁寧に案内するので、指示に従って動けば問題はありません。
・玉串拝礼
この作法が一番気になるのではないでしょうか。焼香とは全く異なります。
1.神職から玉串を両手で受け取ります。右手で玉串の根本を上から持ち、左手で葉の部分を下から支えるように持ちます。
2.玉串を置く祭壇の三歩手前まで進みます。小さく一礼してから進み、今度は深く礼をします。
3.玉串を祭壇と水平にし時計回りに回して、玉串の根本を御霊前に向けて静かに置きます。
4.二拝(2回お辞儀)、二偲び手(音をたてずに拍手)、一拝して終わりです。
この時も神職が丁寧に説明をします。わざわざみんなの前に出るのが、嫌だなと思う人いるかもしれませんが、あとはみんなで一礼するだけです。
神葬祭 その他
「厳かで慎み深く簡素」と表情しましたが、葬儀は全体的に静かだと思います。
神職が会場に入る時や玉串拝礼の時に古典的な音楽を流しますが、それ以外はシーーンとしてます。
祭詞を奏上する時も木魚のような道具はなく、神職だけの声が会場に渡ります。
だからこそ、「厳かで慎み深く簡素」なのです。
「各地域特有の特徴がある」も、各地域の文化や風習が反映されたり、その神社だけに伝わるやり方などもあると思います。基本的に宗派は無いので、今何をしているのか理解はできますが、細かいところに違いを見つけることがあります。
「制約が少なく費用も抑えられる」は、仏式のお葬式と比べた時のことです。神葬祭でお金を高く支払ったから豪華で壮大な神葬祭になることは別にありません。やることは全部同じです。
故人の帰幽した後の名前を決めることも霊璽に書くことも無料です。年齢や性別で名前で決めることになっているので、いくら高額な課金して有り難い名前にすることは出来ません。平等に名前を付けます。
・他宗教を信仰していても良いのか?
問題はありません。多くの場合は仏教徒もしくは無宗教の人だと思います。
「神道を信仰していないと無理だ。ってことも無いですし、新興宗教団体の信者でも参列は問題ありません。故人の最後のお別れには、ちゃんと参加して欲しいです。
ここまで読んでくれて、ありがとう
良い一日を