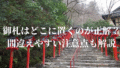最近神社にお参りしに行きましたか?
「神社に参拝する時って、どういう作法が正しいお参りの仕方なんだろう?」と思った経験ありますよね。
神様にご挨拶するから失礼なことはしたくないですよね。
今回は現役の神主である筆者が、事前に知っておきたいお参りの基本作法や豆知識をご紹介します。
神社の正しい参拝方法

神社のお参りの作法に、厳格なルールは存在しないんです。
重要なことは、心を込めてお参りすることです。
参拝の決まり事は存在しない。と伝えましたが、
「神様に失礼がないようにお参りすべきだよね」の観点から、守った方が良いことはあります。
しかし、その参拝方法が全国どこでも一緒ってことではありません。
日本には八百万の神々がいるので、神社や地域によっても特色があります。
ですので、当たり前だと思っていた作法が、他のところでは通用しない場合もあります。
では、今回は一般的な参拝作法を紹介します。
神社の正しい参拝方法 鳥居をくぐる前に一礼をする

神社と言えば鳥居のイメージが強いと思います。
鳥居は神様がいる場所と外の世界を分ける境界の役割をしていると言われています。
鳥居をくぐると神様の領域です。
取引先を訪問する際に失礼な態度はしないですよね?
そのような気持ちで、神社を参拝する際は鳥居をくぐる前に一礼してお邪魔します。
そして参拝を終えて帰る時も、鳥居をくぐって向き直し一礼した方が良いです。
一礼するのが恥ずかしいと感じる人もいるかもしれませんが、
全然気にしないでください。
多くの参拝者が一礼しない中、綺麗な一礼する参拝者を見かけると、
神職たちからの評価は上がります。
神社の正しい参拝方法 参道を歩く時は端っこを歩く
参道の真ん中を「正中(せいちゅう)」と呼びます。
鳥居の真ん中から社殿の中で祀られている鏡までの真ん中を「正中」と呼ばれており、
神様の通り道だと考えられています。
鳥居をくぐる時は、真ん中で一礼するのではなく、左右のどちらかに寄ります
神社の正しい参拝方法 手水舎で手と口を清める

御拝殿に近づくと、手と口を清める御社殿の近くに、手と口を清めるための手水舎が見えてきます。
さて手水舎をなんて読みましたか?「ちょうずや」と読みました?
実は「てみずしゃ」と読むのが、神社界としては正しい読み方になっています。
お清めせず穢れたまま参拝してしまう参拝者が最近増えていますが、必ず手と口清めましょう。
柄杓あり・なしで作法が変わりますので、それぞれ簡単に説明します。
柄杓ありの場合
- 落ち着いた心で、一礼する
- 右手で柄杓を持って水をすくい、左手を清める
- 左手に持ちかえて、右手を清める
- 右手に持ちかえて左手に水を溜め、口を清める
(※直接口を柄杓に付けない) - もう一度、左手を清める
- 柄杓を手前に傾け、持ち手部分を清める
- 柄杓をもとの位置に戻す
柄杓なしの場合
- 心を落ち着かせ、一礼する
- 両手を出し、手を清める
- 両手で水を受ける
- 口を清める
- 両手を清める
上記が基本的な手順になります。
以上を1杯の水で済ませるのが美しい所作だと言われます。
地域によっては、パンっと一度柏手を打つ神社もあります。
神社の正しい参拝方法 お賽銭を納める時の順番は?

お賽銭箱の上に鈴がある場合は、鈴を鳴らします。
その音色で、祓い清め、神様にご自身の存在を知らせるという意味があると言われてます。
鈴を鳴らした後、お賽銭を入れます。
お賽銭の語呂合わせを気にする人もいますが、ソレに関しては否定派です。
有名占い師やスピリチュアル系インフルエンサーが色々と紹介していますが、単なる語呂合わせで、彼らが勝手に言っているだけのマナーです。
もっと正直に言うと、小銭よりお札の方が助かります。
お賽銭は本当に貴重な収入源です。
しかし、小さな神社だと一日数百円の事例もあります。
近年苦しいことが、銀行に預ける時にしっかりと手数料を取られることです。
この手数料が結構キツイんです。
神社の正しい参拝方法 お参りは「二礼二拍手一礼」

お参りの基本作法は二礼二拍手一礼ですが、神社によって拍手が多いところも存在しています。
1.二礼
姿勢を正して、90度の深いお辞儀を2回行う
2.二拍手
胸の高さで右手を少し引いて2回叩きます
3.手をきちんと合わせ、心を込めて祈る
(最近手を合わせたまま、お辞儀をする参拝者が増えています)
4.一礼
再び姿勢を正して深いお辞儀をする
多くの神社には、やり方を教えてくれる看板があるので、それに従うと良いです。
神社の正しい参拝方法 その他よくあるマナーの疑問Q&A
ここからはお参り前に知っておきたい豆知識やマナーをQ&A方式でお伝えします。
御朱印はいつもらえばいいのか
参拝した後にいただくようにしましょう。
当然ですが、御朱印は記念スタンプではありません。
お参りしてから御朱印を書いてもらうのが一番良いです。
受付の時間に限りがありますし、担当者が不在などで授与できない場合もあります。
行きたい神社のHPを事前に確認しておくのが一番良いです。
引いたおみくじはどうするか
専用の結び台が用意されている場合は、そちらに結ぶようにしてください。
おみくじを結んでもよい木があるなら、必ずそちらで結んでほしいです。
時々、変なところに結んでいく参拝者がいます。
シンプルに迷惑なので止めてほしいです。
おみくじの吉凶だけを判断すのではなく、書いてある内容も読んで、その後の生活の指針として役立てていってほしいです。
実は持って帰ってもいいです。
ときどき読み返すのも良いとされ、筆者は持って帰る派です。
お守りを買うタイミングは?
お参りした後なら、いつでも大丈夫です。
お守りはいくつも持っていていいの?
問題ありません。
「たくさん持っていると神様同士がケンカしてしまうのでは?」と言われます。
でも気にする必要はないです。
日本には八百万(やおよろず)の神様がいらっしゃると考えられているので、それぞれの「ご神徳」で守ってくれるので、いくつ持っていても構いません。
古いお守りの返し方は
一年間ご加護を願ったお守りは、お焚き上げをしてもらいましょう。
上記の案内が神社で言われる一般的な案内ですが、一年以上経っていても身に付けていても問題はありません。
その場合は自分の中で「このお守りは役目を終えた」と感じた時に、感謝の気持ちを込めてお参りに行き、神社にお返ししましょう。
参拝時の服装に決まりはあるか

厳格な決まりはありません。
気軽にお参りする場合は、気にすることはありません
ところが、神社でご祈祷を受ける時は注意が必要です。
特にお宮参りや七五三などのお参りで、神聖な場所である御社殿でご祈祷を受ける場合は、スーツや着物など、できる限り正装をすべきです。
ラフな服装は神主さん達に軽蔑されます。
もちろん経済的状況で仕方ない服装であれば、何も思いませんし何も言いません。
しかし、おしゃれにラフな服装してサンダル履いたら最悪です。
神社によっては、靴を脱いでご祈祷を受ける場合もあります。
その際に裸足であった場合は、怒られることもあります。
いい大人がみんなの前で怒られるのは、本当に最悪な状況です。
特に夏の時期だとサンダル履いてくる参拝者が増えるので注意してください。
神社の正しい参拝方法 まとめ
どうだったでしょうか?
人によっては、一年に2・3回しか神社に行かない人もいますが、もっと気軽に訪れても良い場所なので、来てください。
個人的には、実際にご祈祷を受ける時だけ服装に気を付けてもらえば、大丈夫です。
ここまで読んでくれてありがとう
良い一日を

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b417cc5.89704830.4b417cc6.22d1744e/?me_id=1374281&item_id=10000196&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fplussmile%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-5%2F20250727075333_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49b3f1f5.b1d337bc.49b3f1f6.c5393125/?me_id=1235962&item_id=10201844&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkurashikenkou%2Fcabinet%2Fjisyakura2%2Fimgrc0097949300.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)