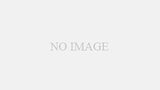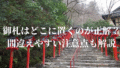無事に推薦状を得られたとしても、次は講習会を主催する大学側の条件をクリアする必要があります。
ここでは國學院大學の講習会を例に、その代表的な条件と注意点を紹介します。
1.年齢制限
受講できるのは原則として満65歳までとされています。
そのため「定年退職後に神職を目指そう」と思っている方は、タイミングによっては申し込めない可能性もあるので注意が必要です。
2.学歴要件
- 短期大学卒業以上(またはそれと同等以上)
- もしくは現在、大学または短期大学に在籍していること
特に学生の場合、講習会は夏休みの時期と重なることが、ほぼ確実です。
そのため長期休暇をすべて講習に充てる覚悟が求められます。
一方で社会人の場合は、長期の休みを確保する難易度がさらに上がります。
実際には仕事を休職した人や退職して参加した人もいました。、貯めていた有給休暇をすべて使って乗り切ったといた人もいました。
3. 事前試験が導入
以前は推薦状さえ揃えばほぼ参加できましたが、現在は事前の選考試験が行われるように。
その背景には、コロナ明け最初の講習会での混乱と受講希望者増加を受けてがありました。
数年ぶりの開催となった回では定員40〜50名に対し、特例で150名以上が受講しました。
結果として指導の質が低下し、適性を欠く人が含まれてしまったことが問題に。
それ以降、大学側は講習会受講者を選抜するために導入を決定させました。
推薦状の用意と適性を測る試験を通過しなければなりません。
4. 1ヶ月で習得すべき内容は「4年分」
講習会の内容は、通常は大学の神職課程で数年かけて学ぶ知識や作法を、わずか1ヶ月で詰め込む超短期集中型です。
信じられないほどの速さで進行するため、予習・復習の習慣や自主的に学ぶ姿勢が求められます。
筆者の実感
講習会を「短期間で資格が取れるラッキーな方法」と考えると、想像以上にギャップがあります。
むしろスタート地点に立つだけでも本気の覚悟が必要な道です。

正座と蹲踞(そんきょ)――神主の基本姿勢はここが違う
神主が座るときの基本姿勢は正座です。
皆さんは普段、正座をする機会はありますか?
きっと今この記事も、椅子に座るかゴロゴロとくつろいだ姿勢で読んでいると思います。
もしよければ、今この場で試しに正座して読んでみてください。
どうでしょう?しんどくないですか?
神職の現場では、祭祀の最中に長時間の正座が求められることもあります。
和風の椅子を使う場面もありますが、問題なく正座ができないと論外とされるほど、基本姿勢として重視されています。
現代の生活では椅子に座ることが主流となり、正座に慣れていない人が多いと思います。
でも私にとって正座以上にキツかったのは、「蹲踞(そんきょ)」という姿勢でした。
蹲踞とは剣道や相撲などで見られる、つま先を立てて踵を浮かせてしゃがむ姿勢のことです。
神職の場合は、そこに膝を床につける姿勢で、全体重がつま先に集中するため、かなりの負担がかかります。
筆者は10分以上は、とても維持できませんでした。
それでも講習会では容赦なく指導されますし、ご祈祷中にも長時間の正座の後に平然と立ち上がる所作が求められます。
あ、まだ正座を続けて読んでくれていますか?
「そろそろ限界…」という方もいるかもしれませんね。
でも、それが神主になるための基礎体力でもあるのです。
社会人と学生、それぞれの苦労
社会人にとって、約1ヶ月の講習会に参加するのは想像以上にハードです。
有給休暇をフルに使う人、思い切って退職する人、夜だけ副業を続ける人など、時間と生活のやりくりに四苦八苦している姿を多く見ました。
一方で学生は、せっかくの夏休みを丸ごと講習会に捧げることになります。
当然アルバイトはできず、収入ゼロ・支出ばかりという現実に不安を感じる人もいました。
さらに地方在住者の負担は大きく、東京までの交通費や1ヶ月分の生活費、宿泊先の手配まで必要です。
家族を持つ人や貯金が限られている人にとっては、経済的な準備も試練のひとつになります。
だからこそ、どちらの立場でも早めの情報収集とスケジュール管理が重要です。
ぜひ、コチラも読んでほしいです。
ここまで、読んでくれてありがとう
良い一日を